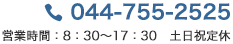

トップ > 社長ブログ
blog
2021-01-27
一昨年、渋谷・神宮前にある設計事務所に行く途中
渋谷駅から明治通りを原宿方向に歩くと、道路沿いの
宮下公園が再開発されている風景を目にしました。
_1.jpg)
渋谷から新宿方向に向って山手線に乗ると
右側の窓からいつも眼下に見える細長い公園が
3階建てに半円のアーチが乗った形になっていました。
それが昨年の夏完成してオープン、年が明けて初めて
訪れました。公園は「MIYASHITA PARK」と横文字になり
商業施設とホテルも一体となった複合施設です。
宮下公園の開設はちょうど私が生まれた1953年。
この地域は旧皇族の梨本宮家があって、当時宮下町と
呼ばれていたことからその名前が付いたとのこと。
.jpg)
1966年には鉄道敷と同じ高さの人工地盤を作って
下を駐車場とした「東京初の空中公園」となりました。
ただ1990年頃から多数のホームレスが住むようになり
老朽化もあり、思い切った再整備が計画されたようです。
さて先入観なく現地に行ってまずビックリしたのは
1階の店舗にルイ・ヴィトン、グッチの高級ブランドが
入っていたことで、3階までのフロアに約90店舗が出店。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_1.jpg)
屋上に上がると広々とした芝生の広場やグランドを始め
ボルダリングウォール、スケボー場とスタバまであります!
.jpg)
_1.jpg)
一番原宿寄りはホテル棟。カフェ・ラウンジから入って
奥にチェックインカウンターなのですが、セルフで無人!
これは三井不動産グループの新しいタイプのホテルです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
変容する渋谷…。駅から歩いて数分のところにまた
画期的な複合施設ができました。
テーマ名
ページ作成日 2021-01-27
2020-12-25
皇居・半蔵門の向かいの国立劇場で、先週家内が
日本舞踊の会に出演しました。この界隈にはある意味で
日本を代表すると言える建物2棟が存在しています。
_2.jpg)
地下鉄の名にもある半蔵門は、広大な皇居の西端にあたり
東の大手門と正反対に位置していて、天皇や各皇族が日常
皇居への出入りするときは主にこの門が用いられるそうです。
名前の由来は、警備担当だった徳川家の家来・服部正成
正就父子の通称「服部半蔵」から来ているとのこと。
伊賀忍者で有名なのはこの家系の初代でした。
.jpg)
_2.jpg)
半蔵門駅で降りてお濠端へ出てから内堀通りを右に折れると
外壁が木材を井桁に組み上げたようないわゆる校倉造り風の
横方向がとても長い建物、国立劇場が出現します。
伝統芸能の上演を目的にした劇場の建設は戦前から何度か
検討されたそうですが実現せず、昭和30年代になってやっと
計画が具体化して設計コンペが行われ、竹中工務店・設計部の
岩本博行案が当選し、昭和41年に竣工しました。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1746席の大劇場と630席の小劇場ほか、資料室や研修室
などから成り、家内はこの小劇場に出演。このコロナ禍で
楽屋の出入りも検温・消毒など劇場係がピリピリしている中
「鷺娘」を約30分舞って滞りなく終演、私もホッとしました。
.jpg)
.jpg)

国立劇場に隣接する最高裁判所は、昭和44年に改築のための
設計コンペが行われ、鹿島建設・設計部の岡田新一案が当選し
昭和49年に完成、その頃建築科に在学中の私は見学会に参加しました。
こちらの外壁は白い御影石張りで司法の頂点という重厚感を出し
内部もほぼ御影石張りで少し寒々しく感じたおぼろげな記憶が…。
岡田氏はこれを契機に独立して様々な公的建築を設計しています。
.jpg)
_1.jpg)
その時、写真を撮った気がしたので探すと出てきました!そして
権威の象徴としての威圧感は約47年前の記憶の通りでした。
_1.jpg)
_1.jpg)
.jpg)
テーマ名
ページ作成日 2020-12-25
2020-11-27
神代植物公園…いつか散策したい場所の一つ。私が子供のころ
親に連れられて来たような気もするのですがハッキリしません。
先日、武蔵野市で行われた工事の地鎮祭の帰る途中、車が
とても大きな林の間を抜けたとき、そこが神代植物公園だった
ことが分かり、それがきっかけになって訪問しました。
隣接する深大寺の開山は奈良時代の天平5年、その周辺は
深大寺村と呼ばれていたのが明治期に神代村に変更されました。
昭和15年調布飛行場の周辺約70万㎡が防空緑地になり
これを「神代緑地」と命名。戦後この内3/4は農地に返上され
残りが「神代植物公園」として昭和36年に開園したのです。
.jpg)
.jpg)
大きなケヤキが並ぶ正門を入り、懸崖造りの菊花展を見ながら
まずバラ園へ。秋バラもそろそろ終わる時期ですがウチの庭
にもあるアイスバーグ、ピエール・ド・ロンサール、ピース等
まだ十分咲き誇っていました。
.jpg)
.jpg)
バラ園の中央にある長方形の噴水池はタテが6~70mありそうな
大きなもので、池越しに見える休憩所は12本の円柱に支えられる
西洋風な立派なもの。ヨーロッパの宮廷を模したのかもしれません。
.jpg)
.jpg)
噴水池を中心に休憩所の反対側には大温室があり、その前面には
9つの鐘が吊られているツリーを模したモニュメント。この公園には
これ以外にも幾つもの彫像がありモダンアートも楽しめるのです!
.jpg)

_1.jpg)
.jpg)
.jpg)
そこから芝生広場に向かう途中、素晴らしい秋の水辺の風景に
出会いました。池の表面を覆っているのはラクウショウというスギ科
の木の葉で鳥の羽のような形なのでそう呼ばれているそうです。
.jpg)
.jpg)

.jpg)
広場に出ると遠くに大きなススキのような穂が見えました。
近くへ行くと高さが4,5mあり、南米原産のパンパスグラスと
いう植物でシュールな感じ。回りを2,3周して眺め続けました。
結局全部は見切れず、来年の春に楽しみを取っておきます。
.jpg)
.jpg)
テーマ名
ページ作成日 2020-11-27
| << | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間:8:30~17:30 土日祝定休
営業時間:9:30~18:00 火水祝定休